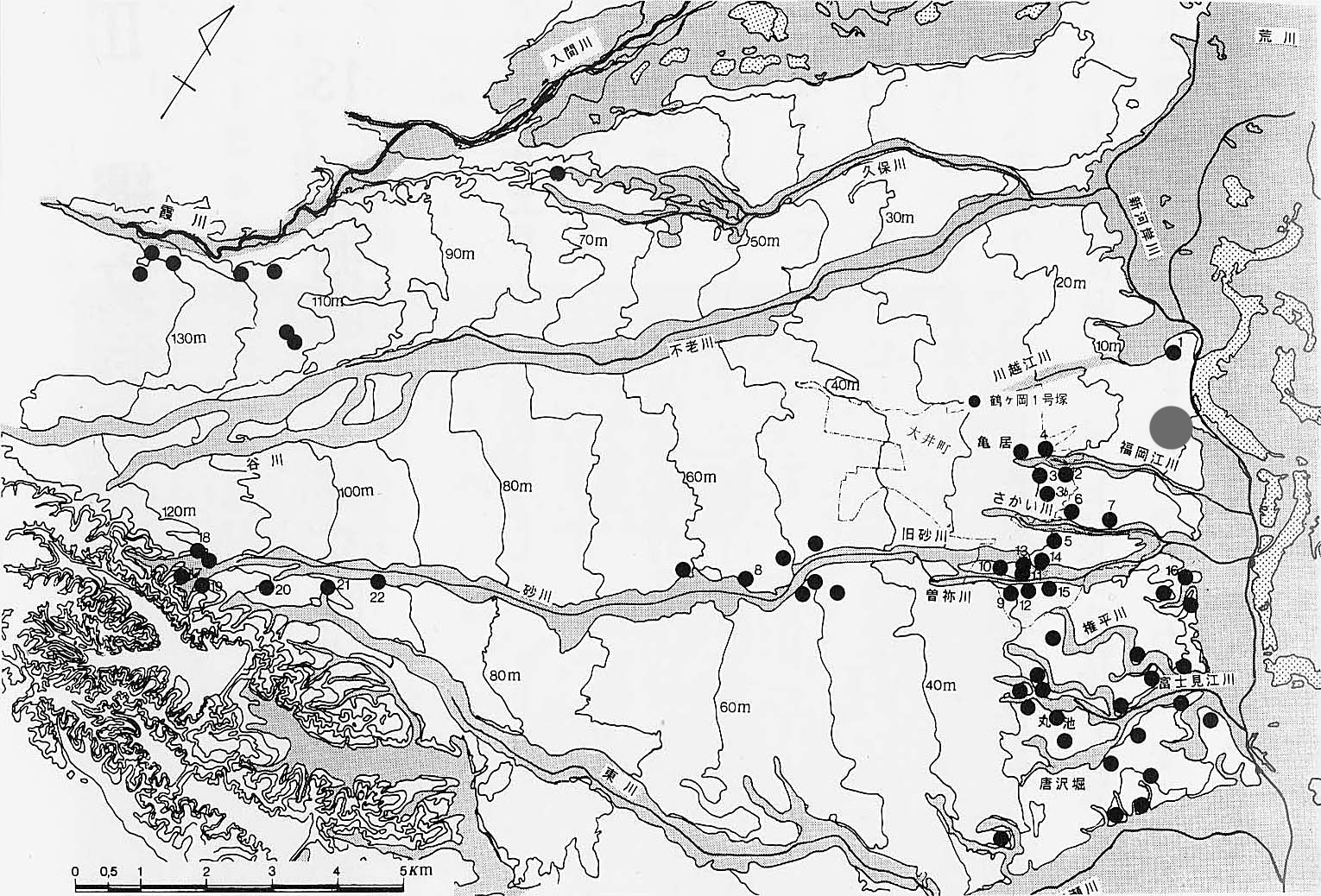
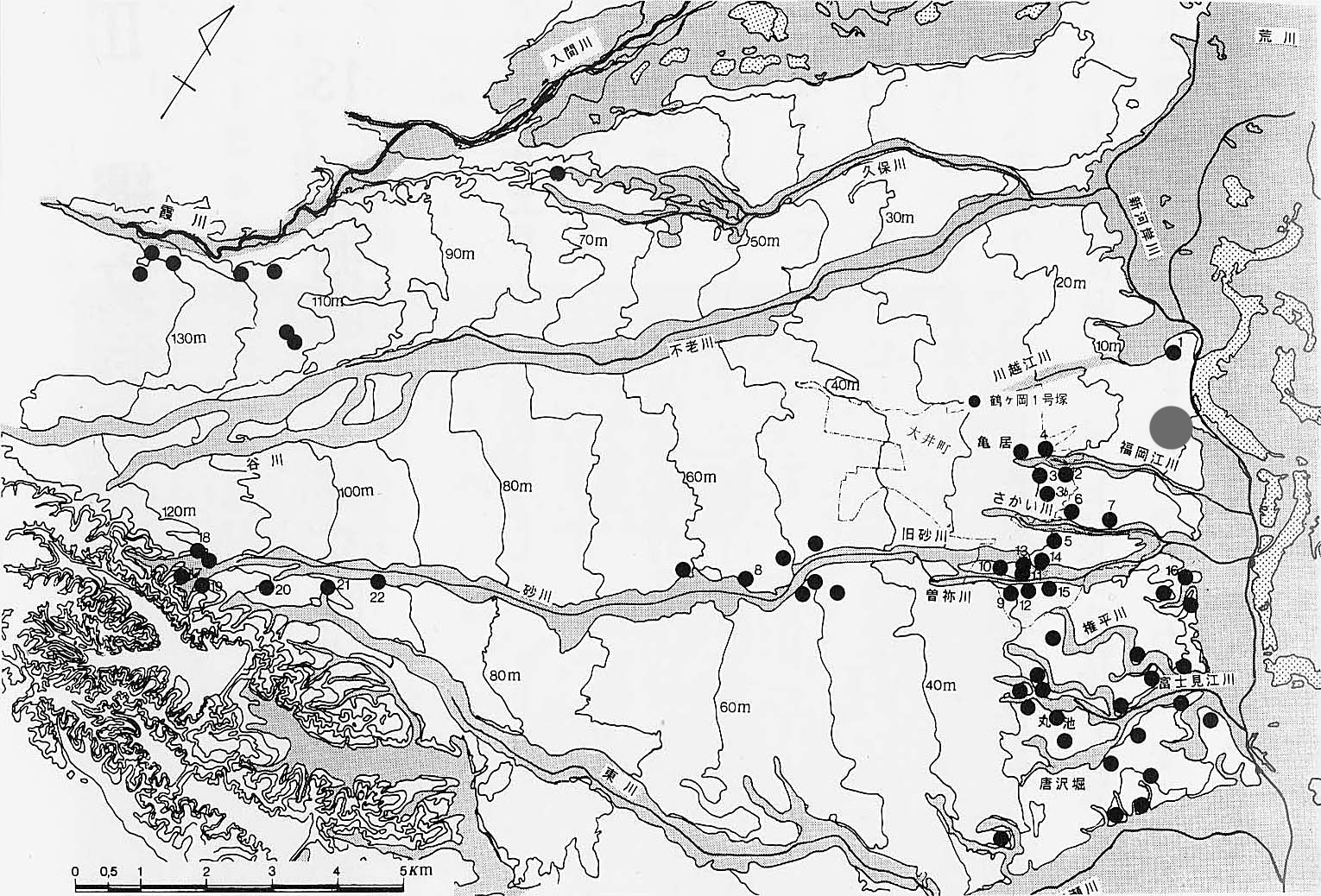
武蔵野台地は、青梅市を河口とする広大な扇状地で、5万年前頃に古い多摩川によって運搬された山地の砂礫が大量に堆積して形成された武蔵野礫層が原形とされている。
この武蔵野台地は、北西から北側を入間川、北東から東側を荒川、南側を多摩川によって限られ西側の関東山地山麓から東端の山の手台地までの東西約50キロメートルの長さを持つ。
武蔵野台地から発掘される遺跡は、人類が居住できるようになった2万年前頃の旧石器時代の物が最古である、とのこと。
武蔵野台地の北東端付近は今の川越で、入間川を北に渡った処にあった河越が川越発祥とされている。
川越から不老川を南に越えた処に福岡村があり弥生時代末から古墳時代初頭の墳墓とされる権現山古墳が今の新河岸川を臨む見晴らしの良い崖上に築かれている。
この高台を南西に下った処に主テーマの発端となった長宮氷川神社がある。